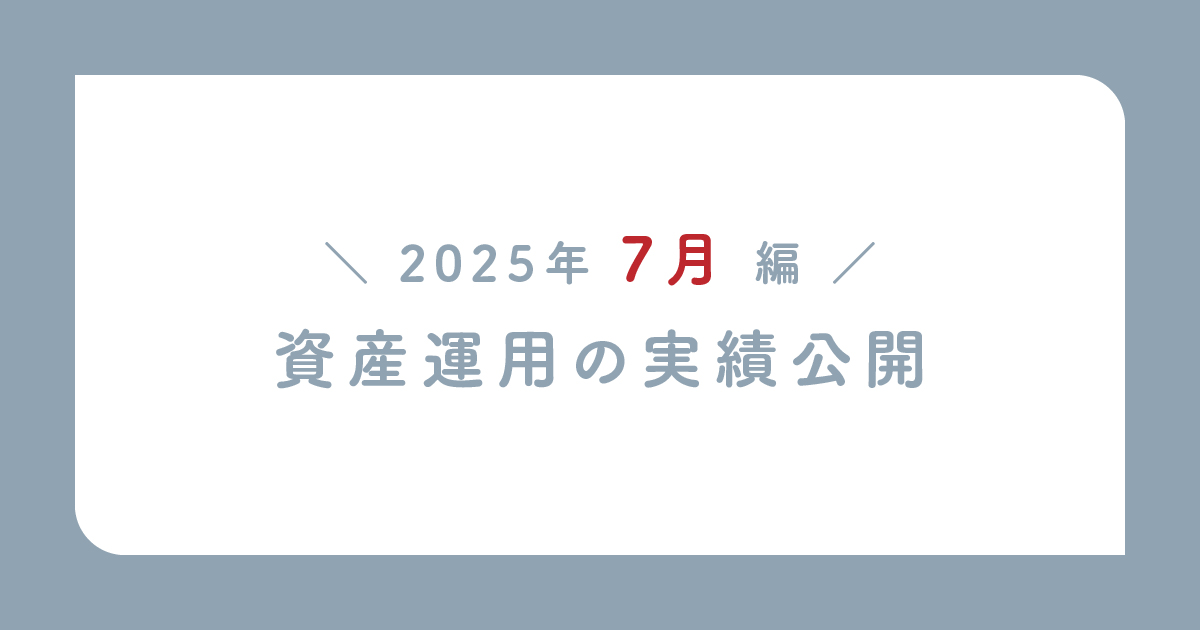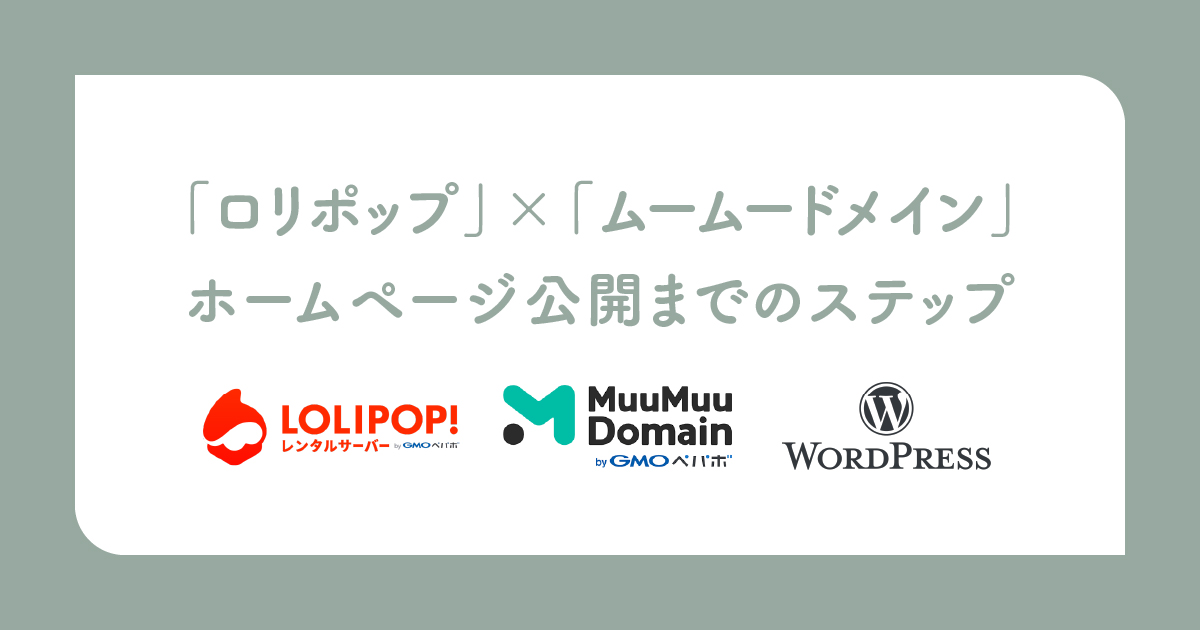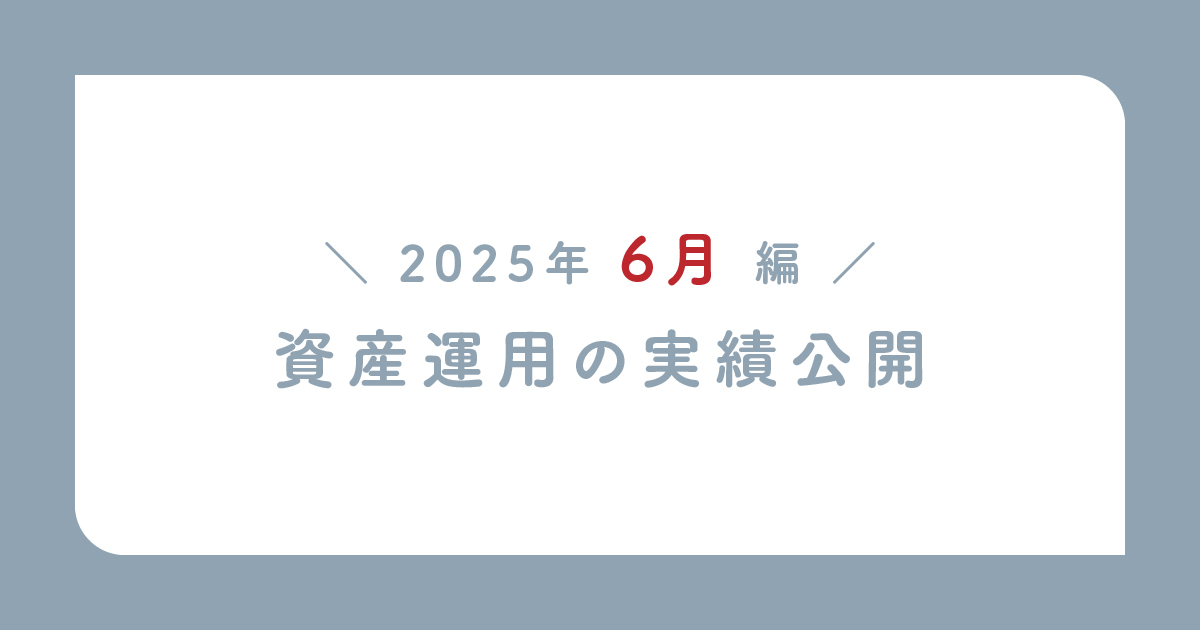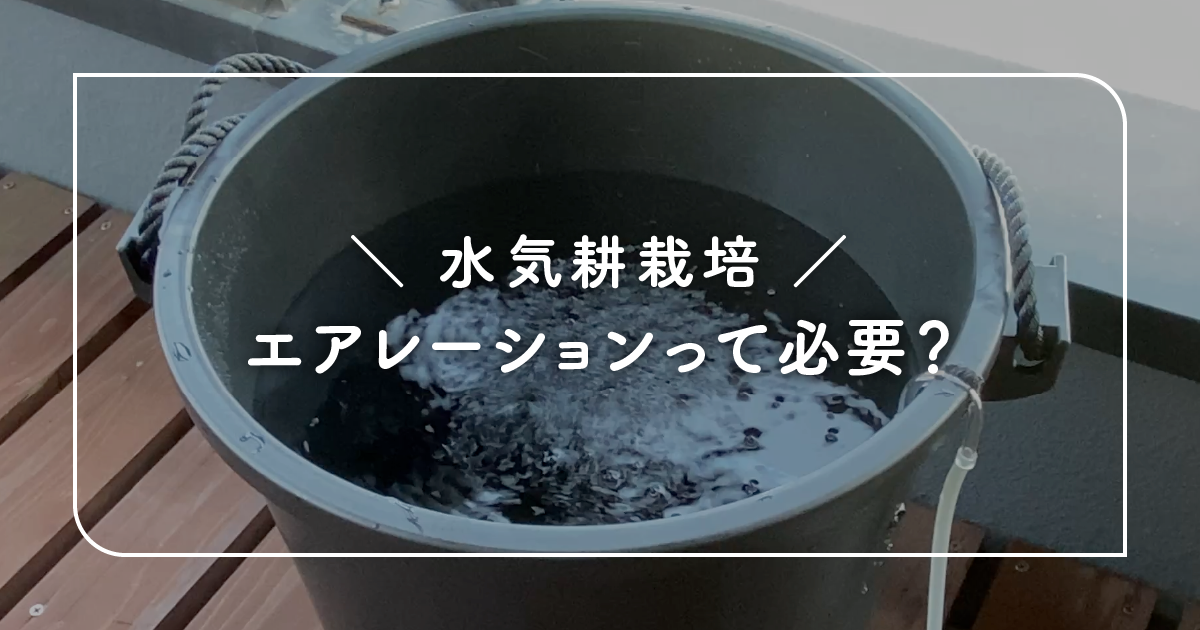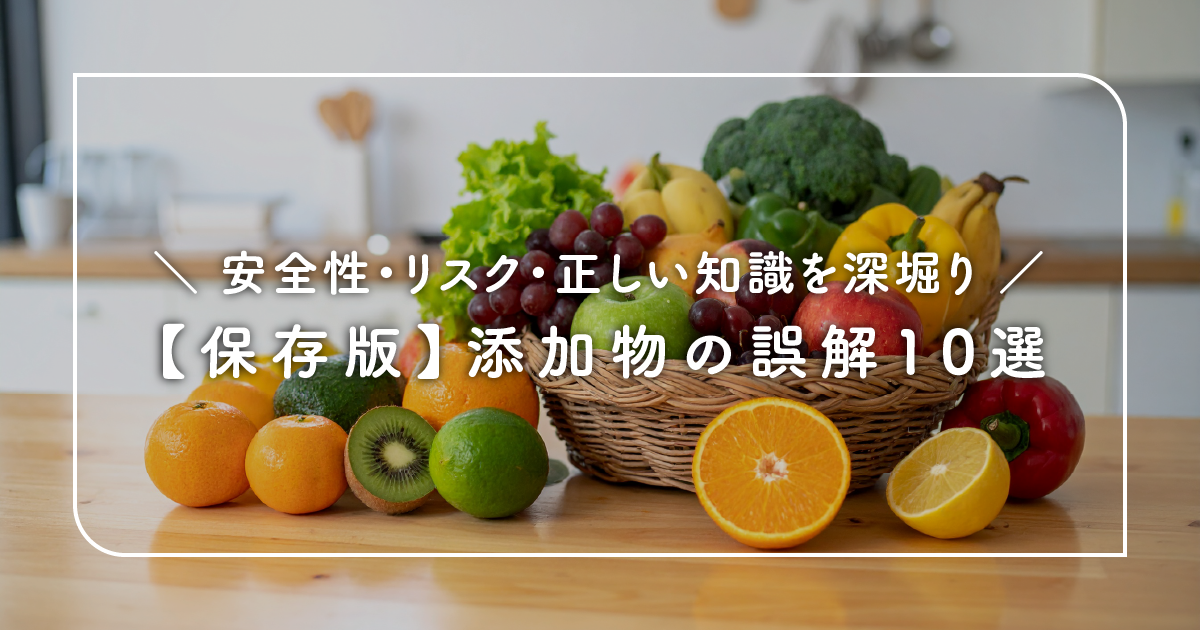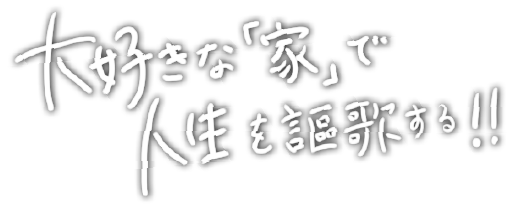こんにちは!リュウセです。
最近、オーガニック食材や無添加食品が注目されるようになりましたよね。
私も「添加物って体に悪いんでしょ?」と、なんとなくそんなイメージを持っていました。
でも、よく考えたら詳しいことは知らない…。それなら一度ちゃんと勉強してみよう!と思い立ったんです。
調べてみると、意外にもイメージとは違う現実が見えてきました。正しく知れば、怖がる必要はないし、むしろ豊かな食生活を支えてくれていることが分かりました!
この記事では、そんな体験をもとに、添加物についての正しい知識をみなさんと共有したいと思います!
添加物とは?
そもそも添加物って何?と思う方も多いですよね。
食品添加物とは、食品の製造や保存、味や見た目を良くするために使われる物質のことです。日本では、厚生労働省が安全性を厳しく審査し、使用できる種類や量を細かく決めたうえで認可しています。
たとえば、パンに使われるイーストフード、ジュースのビタミンC、保存のためのソルビン酸なども添加物の一種です。要するに、添加物は私たちの食生活を支える「裏方さん」みたいな存在なんです。
添加物の誤解10選

さて、ここからは、私が実際に調べてみて「へぇ〜そうだったのか!」と驚いた、添加物に関する誤解をひとつずつ紹介していきます。
なんとなく抱いていた不安やモヤモヤが、少しでもスッキリすればうれしいです。それでは、さっそく見ていきましょう!
1. 添加物は体に悪いの?
「添加物=体に悪い」というイメージを持っている方が多いかもしれませんが、実際にはほとんどの添加物は、安全基準を守った範囲で使用される限り、健康へのリスクは極めて低いとされています。
例えば、食品添加物には許容摂取量(ADI)という基準が設けられており、この基準に従う限り、長期的に摂取しても健康に影響はないとされています(出典:厚生労働省)。
また、FDAやEFSAなどの国際的な規制機関も、食品添加物の安全性について厳格な審査を行い、健康リスクはほとんどないとしています(出典:FDA Food Additive Status List)。
とはいえ、一部の人々にはアレルギー反応や過敏症を引き起こす可能性があるため、成分表示を確認することが重要です。総じて、適切に使用された添加物は、健康に害を与えることはほとんどないと言えるでしょう!
2. 天然由来の添加物は安全、合成は危険?
「天然だから安心」「合成だから危ない」というイメージもありますが、これも誤解のひとつ。
例えば、自然界にはフグ毒や青酸カリのように強力な毒物も存在します。一方、合成された添加物の中には、何十年にもわたって研究され、安全性が確立されているものがたくさんあります。
要するに、大事なのは“由来”ではなく“安全性が科学的に確認されているかどうか”なんです。だからこそ、天然か合成かにこだわるより、しっかり安全審査を受けているかをチェックしたいですね。
3. 無添加食品は絶対に安全?
“無添加”ってパッケージに書かれていると、つい安心して手に取ってしまいますよね。でも実際には、無添加食品にもリスクはあるんです。
農林水産省の資料によれば(農林水産省より)、保存料を使わないことで、カビや雑菌が繁殖しやすくなるケースもあります。特に夏場や保存環境が悪いと、食中毒のリスクが高まることも。
“無添加”という言葉だけに頼らず、購入後の保存方法や消費期限にも注意するのが本当に賢い選び方です!
4. 海外では添加物を使っていない?
「海外、特にヨーロッパでは添加物を使っていない」「日本は添加物だらけ」といった話、聞いたことがあるかもしれません。
でも実際のところ、海外でも食品添加物はしっかり使われています。ただ、日本と比べると認可されている添加物の種類は少ないのは事実です。
たとえば、アメリカ(FDA)で認可されている添加物は約800種類程度、日本では約1500品目ほどが使用可能とされています。
じゃあ海外のほうが規制が厳しいの?というと、これまた単純ではありません。
アメリカでは「GRAS(Generally Recognized As Safe=一般に安全と認められている)」という制度があり、企業が独自に安全と判断したものについては、国の審査なしでも使える場合があるんです。
一方で、EU(ヨーロッパ連合)は比較的新しい科学的データに基づき、使用禁止や制限を柔軟に見直す傾向があり、特定の添加物に関しては日本より厳しい基準を設けていることもあります。
つまり、海外=安全、日本=危険、といった単純な図式では語れないんですね。
国ごとに文化も食生活も違うから、添加物に対する考え方や管理方法も異なっている、というのが本当のところです。
大事なのは、どこの国でも「安全性を確保した上で使われている」という事実なんです!
5. 添加物は一度に大量に摂取しても安全?
これについては注意が必要です。
たとえ安全性が確認された添加物でも、基準を大きく超える量を一度に摂取すれば、何らかの影響が出る可能性はゼロではありません。
FAO/WHO合同食品添加物専門家委員会(JECFA)が設定しているADI(許容一日摂取量)は、「一生涯、毎日取り続けても問題ない量」をベースにしています。
それを考えれば、普通に食べているぶんにはまず問題ありませんが、例えばサプリメントなどで特定成分を極端に取りすぎるとリスクが高まる場合もあるので、やっぱり“バランスよく食べる”が基本ですね!
6. 防腐剤はすべて危険?
防腐剤と聞くと「なんか体に悪そう」と思ってしまう気持ち、よくわかります。でも実は、防腐剤は食品の安全性を守る重要な役割を果たしているんです。
日本食品化学研究振興財団の情報によれば(参考サイト)、防腐剤がなければ、食品がすぐに腐敗してしまい、結果的に食中毒のリスクが大幅に上がってしまいます。
もちろん、防腐剤にも使用基準があって、必要最小限の量しか使えないルールになっています。適正な量で使われる防腐剤は、むしろ私たちを守ってくれている存在なんですね。
7. 着色料は無意味?
「どうせ色をつけるだけなら、なくてもいいんじゃないの?」と思うかもしれませんが、実は着色料にも大切な役割があります。
日本食品添加物協会によると(参考ページ)、食品の見た目は食欲やおいしさの感じ方に大きな影響を与えるんです。
例えば、鮮やかなオレンジ色のジュースや、きれいな緑色の抹茶菓子を想像してみてください。もしそれがくすんだ色だったら、ちょっと食欲が減っちゃうかも?着色料は食品の鮮度感やおいしさを視覚的にサポートしているんですよ。
8. 添加物がアレルギーを引き起こす?
これは「絶対ない」とは言い切れません。
厚生労働省のデータによると、特定の添加物(例:亜硫酸塩など)がアレルギー症状を引き起こすことがあるとされています。
ただし、こうしたリスクは極めて稀であり、さらに義務表示対象になっているため、食品表示を確認すれば対策可能です。
特別な体質を持っていない限り、通常の食生活ではあまり心配する必要はありません。安心して、美味しいものを楽しみましょう♪
9. 有機食品には添加物が使われない?
有機食品=無添加、と思っている人も多いですが、実際は違います。
有機JAS制度のガイドラインを見てみると、食品添加物の中でも「認められたもの」に限り、使用が許可されています。
例えば、凝固剤や保存料の一部などがこれに該当します。つまり、有機食品でも加工上必要な添加物は使われている場合があるんです。
“有機”という言葉だけで判断せず、きちんと表示を確認することが大切ですね!
10. 添加物は将来的に禁止されるかもしれない?
科学は日々進歩しているので、将来的に「この添加物は使用禁止」という判断が下されることもあり得ます。
欧州食品安全機関(EFSA)でも、新たな研究結果に基づいてリスク評価を更新し、必要に応じて使用禁止や規制強化を行っています。
でも逆に言えば、常に最新の科学で見直しが行われているからこそ、私たちは今の食品を安心して食べられるんですね。食品の世界も、絶えず進化しているんです!
まとめ
今回、添加物についてじっくり調べてみて、「添加物=悪」という単純な考え方は、ちょっともったいないなと思いました。
もちろん、何でも過剰に摂ればリスクはありますが、普通にバランスよく食事をするぶんには、ほとんど心配いらないことがわかりました。
むしろ、添加物のおかげで安全でおいしい食べ物が手軽に楽しめているんですよね。
正しい知識を持って、賢く選び、上手に付き合うことで、もっと安心して、もっと豊かな食生活を送れるんだと思います。これからも、自分の目で成分表示をチェックしながら、楽しんでいきたいですね!